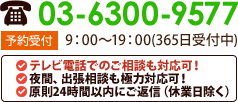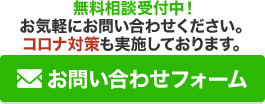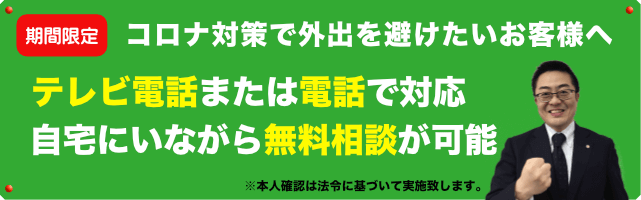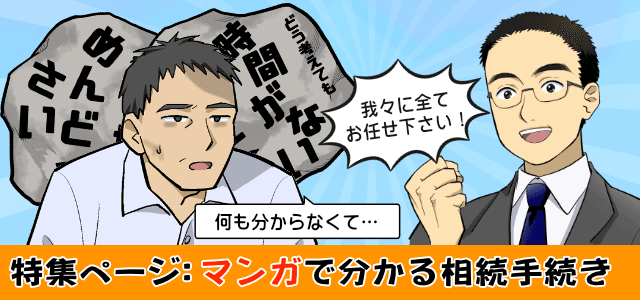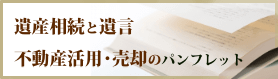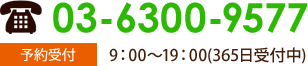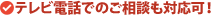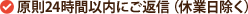2019年10月号の「相続・贈与マガジン」は、2020年から施行予定の「配偶者居住権」や、増税後の住宅購入を支援する「住宅取得資金贈与制度」について解説しています。
2019年10月号 目次
- 41.9%とは? 数字で見る相続
- 配偶者に住む家を残したい!2020年から施行予定の『配偶者居住権』とは
- 増税後の住宅購入を支援する『住宅取得資金贈与制度』とは?(2)
- 生前贈与と相続、どちらが節税できる?
- 「相続・贈与マガジン」を読みたい方へ
41.9%とは?数字で見る相続
2018年12月に国税庁が発表した『平成29年分の相続税の申告状況について』によれば、2017年中に相続税申告のあった相続財産のうち、土地及び家屋が占める割合は41.9%でした。
主な相続財産は自宅不動産で、現預金は少ない一方、相続人は多数いるという場合、財産を分割するために配偶者や子が被相続人と住んでいた家を手放すことになったり、相続税の納税が困難になったりするおそれがあります。相続財産における不動産の割合が高い人は対策を考えておきましょう。
今回の「相続・贈与マガジン」では、2020年施行予定の改正民法の一つで、遺される配偶者が相続開始後も自宅に住み続けられる『配偶者居住権』について取り上げています。ぜひご一読ください。
配偶者に住む家を残したい!2020年から施行予定の『配偶者居住権』とは
自分の死後も、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものです。しかし、配偶者が自宅を相続しても、ほかの相続人が預貯金などの財産を相続したことで、生活費や相続税の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがあります。
今回は、そういった問題を解決するために新設される『配偶者居住権』について解説します。
相続財産のほとんどが自宅の場合配偶者に起こる相続リスク
相続財産のなかで自宅不動産の財産価値が最も高く、その自宅以外の財産としては、少しの預貯金以外にめぼしいものがないというケースは少なくありません。
このような場合、相続の際にどのようなことが起こり得るのでしょうか?
まず、相続人である配偶者が自宅を相続すると、子どもなど、ほかの相続人に自宅以外の財産である預貯金が渡るため、配偶者は、家はあっても生活費が大きく減ってしまうことになります。
また、預貯金の額が相続割合に満たない場合など、預貯金だけでは相続財産が十分に行き渡らない場合、配偶者は自宅を売って分配する財産に充てることになります。
分配財産がなんとか預貯金からまかなえた場合でも、相続税の支払いが必要です。これも払いきれなければ、自宅を売って支払わなくてはならないでしょう。
延納、物納という方法もありますが、いずれの場合も遺された配偶者は、今後の生活資金が不足したり、住み慣れた家を手放す事態にもなりかねません。
このような場合の配偶者の居住権を保護するために考えられ、2020年4月の施行が予定されているのが『配偶者居住権』です。
これは不動産の所有権を、配偶者が死亡するまで住み続けられる『配偶者居住権』と、子どもな どのほかの相続人が、居住権以外の所有権だけを持つ『負担付き所有権』との二つの権利に分ける制度です。
二つの権利に分けることで配偶者の負担が大きく軽減

たとえば、相続財産として資産価値5,000万円の自宅と1,000万円の預貯金があり、相続人は妻と子ども1人というケースでは、法定相続分に従えば、妻が3,000万円、子どもが3,000万円分を相続することになります。
自宅5,000万円を『配偶者居住権』の資産価値2,200万円、『負担付き所有権』の資産価値2,800万円として分けた場合、妻は配偶者居住権の2,200万円と法定相続分との差額の800万円を現預金で受け取れるため、その後の生活の経済的不安も取り除くことができます。
配偶者にとってはメリットの大きい制度ですが、負担付き所有権の相続人にとっては、所有権はあっても、配偶者が生きている間はその家に住むことも、売りに出して現金化することもできず、さらに自分が得られる不動産以外の相続財産も減ってしまうため、トラブルの元になることも考えられます。
配偶者長期居住権については、遺言書に書き残しておくだけでなく、しっかり話し合っておくことが必要です。
増税後の住宅購入を支援する『住宅取得資金贈与制度』とは?(2)
9月号では、消費税増税後でも『住宅取得資金贈与制度』を活用すれば、住宅取得費用を抑えられることをご紹介しました。
しかし、活用しない方が費用を抑えられる場合もあるのです。
今回は、どういう場合に住宅取得資金贈与制度を使わない方がよいかをご紹介します。
『小規模宅地の特例』の方が節税できるケースも

「今は賃貸暮らしだが、親が亡くなった後、実家を相続する」と考えている人は多いのではないでしょうか。この場合、住宅取得資金贈与制度を活用するのは慎重になった方がよいかもしれません。
被相続人である親の自宅を相続する場合、自宅の評価額を最大80%減額にできるという『小規模宅地の特例』という制度があります。たとえば、評価額1億円の自宅であれば、敷地面積330平米までは80%の減額で評価額2,000万円にすることが可能です。そうなれば、相続税そのものがかからなくなる可能性も出てきます。
ただし、どんな場合でも小規模宅地の特例が使えるわけではありません。一定期間被相続人である親の自宅に同居しているなど適用要件があります。(例外あり)
住宅取得資金贈与制度と 小規模宅地の特例の差
住宅取得資金贈与制度と小規模宅地の特例のどちらを活用した方が節税になるのか、ここでシミュレーションしてみましょう。
被相続人である父親が持つ財産は、相続税評価額で1億円相当の自宅と預貯金3,000万円。妻は亡くなっており、相続人は子どもが1人だとします。
たとえば、父親が生前、子どもに住宅取得資金贈与制度を使って3,000万円を贈与したとします。
この場合、1億円相当の自宅のみが相続税の課税対象となり、相続税は1,220万円です。
一方、子どもが親の自宅に同居をしていたとします。この場合、自宅の相続に関しては小規模宅地の特例が使えるため、1億円相当の自宅の評価額は2,000万円となります。預貯金を加えた課税対象額は5,000万円となり、相続税は160万円です。
つまり、小規模宅地の特例を活用した方が、1,000万円以上も節税できる可能性があるのです。
相続税を抑えるためには、実家を相続してそこで暮らす予定があるのか、早いうちから話し合っておくことが重要です。また、相続税や贈与税の試算は、正確な数字を把握することもポイントになるでしょう。
生前贈与と相続、どちらが節税できる?
- 相続税対策をしたいのですが、生前贈与をした方がよいのか、それとも相続をした方がよいのかで悩んでいます。どちらがよいのでしょうか?
- 生前贈与の特例を上手に活用すれば、贈与税も相続税も節税することができます。生前贈与の特例の一つである『暦年贈与』は、用途を問わず利用しやすく、年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないため、おすすめです。

上手に活用すれば相続財産を減らすことができるのが『暦年贈与』です。
ただし、実際に暦年贈与を使って財産を贈与していたにもかかわらず“一つの大きな金額の贈与契約をただ単に分割して渡していただけ”と税務署に見なされてしまうと、連年贈与としてまとめて課税されることもあるため、注意が必要です。
そうした事態にならないためには、“贈与契約書をその都度作成しておく”“自筆で署名、押印する”など、毎年の暦年贈与が個別の贈与契約であることを、税務署に対して明示できるようにしておくことが肝心です。
また、各暦年に関する贈与税特例を使うときも必ず税務署に申請しておかなければなりませんので、忘れないようにしてください。
暦年贈与と見なされても、相続税や贈与税がかかることもあります。まず、相続開始前3年以内に相続で財産を取得した人になされた贈与は、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算されます。また、贈与税がかからないとされる暦年課税の基礎控除額 (年間110万円まで)を超えると、贈与税が課税されます。その場合の贈与税については、相続税を計算 するときに控除されることになります。
贈与税には配偶者控除や住宅取得資金贈与の非課税制度などもあるため、これらを活用することで贈与税を抑えることができます。ただし、生前贈与と相続のどちらの方が節税になるのかは、個別に判断する必要があります。
「相続・贈与マガジン」を読みたい方へ
毎月発行の「相続・贈与マガジン」をもっと読みたいとご希望の方に、PDFファイルをお送りしています。
メールフォームの「お問い合わせ内容」欄に「相続・贈与マガジン」希望と書いて、メールアドレスをお知らせください。